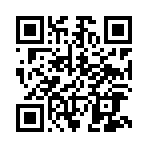2013年02月28日
地名のいわれ
ご無沙汰しております
今日の青空に元気をもらい、久々の更新です
あんまり、多羅尾の寒さばっかりお伝えするのもなんなんで今回は
「多羅尾」の地名のいわれの伝説をご紹介したいと思います
多羅尾には、大昔から、「たら」という木がたくさん自然に成育していました。
そのため、旅人たちや村民の間で「たら野」とか「たらほ」とかよばれていたそうです。
この地名が、現在の「多羅尾」と書く漢字になったのには、古くから次の2つの伝説があります。
①多羅尾には、大昔から『羅尾』という身長3m、そのうちしっぽの長さが半分くらいある獣がたくさん住んでいました。
この獣は、人に害を与えたりしない、毛並みのとても美しくおとなしい動物でした。それで領主の甲賀三郎という人が多羅尾と名付けたと伝えられています。けれどもこの話はただの昔話にすぎません。
②平安朝のはじめ、空海が真言宗の本山「金剛峯寺」をどこの土地に建てようかと近畿地方を調べて歩かれたとき、多羅尾にもこられしばらく滞在されたといわれています。その時、空海がそれまで「たら野」とか「たらほ」と言われていた地名を『多羅尾』と改められたと伝えられています。
どちらの話が本当かはご想像におまかせです

あっという間に2月がおわり、3月に突入です
多羅尾にも少しづつ春が近付いてきているようです

桜はもう少しあとになりそうです(^^;)

今日の青空に元気をもらい、久々の更新です

あんまり、多羅尾の寒さばっかりお伝えするのもなんなんで今回は
「多羅尾」の地名のいわれの伝説をご紹介したいと思います

多羅尾には、大昔から、「たら」という木がたくさん自然に成育していました。
そのため、旅人たちや村民の間で「たら野」とか「たらほ」とかよばれていたそうです。
この地名が、現在の「多羅尾」と書く漢字になったのには、古くから次の2つの伝説があります。
①多羅尾には、大昔から『羅尾』という身長3m、そのうちしっぽの長さが半分くらいある獣がたくさん住んでいました。
この獣は、人に害を与えたりしない、毛並みのとても美しくおとなしい動物でした。それで領主の甲賀三郎という人が多羅尾と名付けたと伝えられています。けれどもこの話はただの昔話にすぎません。
②平安朝のはじめ、空海が真言宗の本山「金剛峯寺」をどこの土地に建てようかと近畿地方を調べて歩かれたとき、多羅尾にもこられしばらく滞在されたといわれています。その時、空海がそれまで「たら野」とか「たらほ」と言われていた地名を『多羅尾』と改められたと伝えられています。
どちらの話が本当かはご想像におまかせです


あっという間に2月がおわり、3月に突入です

多羅尾にも少しづつ春が近付いてきているようです


桜はもう少しあとになりそうです(^^;)



 ですけど、通勤時のこの景色はきれいで結構好きやったりします
ですけど、通勤時のこの景色はきれいで結構好きやったりします